読解力を身につけるって、言葉では簡単ですが実際に学ぶとなると抽象的で難しいですよね。
保護者の皆様も、わが子に読解力を身につけてほしいけれど、何をしたらいいの?と悩まれるかと思います。
ですが、大丈夫です!塾に通わなくても、家庭だけでも読解力は身につきます!!
この記事では、家庭学習で具体的に何をしたらよいのか丁寧に紹介します。
まず、お子様がどこまで文章が読解できているかによって取り組むことは違います。
以下に6つのチェックポイントを設けました。
普段お子さんが長文読解に取り組んでいる様子を見て、つまづきポイントを探してみてください。
読解力チェックポイント
①長文を読むことに抵抗がない
Yes→②の質問へ
No→まずは本を読むことからスタートして、長文を読むことに慣れてみよう!
②最低限の語彙力がある
Yes→③の質問へ
No→語彙力についての学習漫画を読んでみよう!
③書かれた文章の内容を理解している
Yes→④の質問へ
No→文章の要約をパパさんママさん、周りの人にお話ししてみよう!
④長文読解問題で聞かれた問いかけの内容を理解し、記号選択問題は解ける
Yes→⑤の質問へ
No→記号選択問題のパターンと解答の手順を知ろう!
⑤長文読解問題で聞かれた問いかけの内容を理解し、記述問題にとりこぼしがない
Yes→⑥の質問へ
No→記述問題のパターンと解答の手順を知ろう!同じパターンの問題を連続して解いてみよう!
⑥制限時間に余裕をもって長文読解問題に正確に解答できる
Yes→おめでとう!キミは読解マスターだ!!
No→時間制限を設けて文章の要約を書く練習をしてみよう!
以下、家庭学習で具体的に何をしたらよいのか詳細を説明していきます。
お子様の読解力アップのお役にたてましたら幸いです。
まずは長文を読むことに慣れてみよう!
【読解力チェックポイント①長文を読むことに抵抗がない⇒NO!だった方はこちら】
読解力の前の段階で、まず長い文章を読むだけで嫌な気持ちになって内容も頭に入ってこない・・・
そんな状態で問題集を解いても、余計国語が嫌いになってしまう、悪いスパイラルに陥りますよね。
そんなお子様には、まず読書に親しむことからスタートしてみましょう!
子供が本に興味をもつためのポイントは2つあると考えています。
①子供が好きなものをテーマにしている本を選ぶこと
②親が本を楽しそうに読んでいる姿を見せること
①子供が好きなものをテーマにしている本を選ぶこと について
当たり前かもしれませんが、保護者が読んでほしい本ではなく、子供が興味をもっていることに関係した本を選びましょう。
はじめは、いきなり本を購入するのではなく、図書館でいろんなタイプの本を借りてきて試行錯誤するといいかと思います。
お金を出して買ってしまうと、読んでくれないときに親ががっかりしてしまいますしね。
②親が本を楽しそうに読んでいる姿を見せること について
これ、本当に大事です!!意外と実行できている人多くはないのでは・・・?
私は、図書館で借りてきた本をわざと子供の前で読むようにしていました。
時々くすりと笑ってみたり、あぁなるほどねと声に出してみたりです。
そして、読み終わった本は、テーブルの上など目にとまる場所に置いておきます。
忙しい方は30分1時間と読む必要はなく、なんだったら、1日5分でもいいんです。
親が本を読んでいないのに、本は面白いよ、読もうよと話しても説得力全然ないですよね。
子供って親をよく見ているので、親が興味をもつものは気になるものです。
読書初心者さんにおすすめの本についてはこちらの記事に詳しく書いています。
語彙力を高めよう!
学習漫画を読んで語彙力を高めよう!
【読解力チェックポイント②最低限の語彙力がある ⇒NO!だった方はこちら】
書いてある単語や言い回しの意味が分からないと、内容も分からなくなってしまいますよね。
読解力以前の問題で、最低限の語彙力は必要なものです。
もちろん、読書を通じて語彙力を身につけることができれば一番よいのですが、それには時間がかかってしまいます。
そうなると、手軽に速く、楽しく語彙力を身につけるには、語彙力テーマの学習漫画をオススメします!
学習漫画で我が家の一番のおすすめは、
角川まんが学習シリーズ のびーる国語 無敵の語彙力 分かると差がつく言葉1000です!
こちらがおすすめな理由は、まずなんといっても漫画が面白い!!
わが家ではこちらの角川の学習漫画以外に他社の語彙力系の漫画本も購入したのですが、
息子的に面白さナンバー1だそうです。
親の目から見ていいなと思ったところは、全ての語彙に対して4コマ漫画がついていること。
さらに、漫画の中にしっかりと語彙が入っていて、太線赤字で強調されているところです。
どんなに分かりやすい、いい解説がついていても、よっぽど意識の高い子供以外はまずは漫画しか読まないでしょう。
なので、漫画を読むだけで語彙に触れられるというところが大きなメリットなのです。
語彙力アップのおすすめ漫画については、こちらの記事に詳しく書いています。
教科書の音読を徹底することで語彙力を高めよう!
学習漫画以外にもっとすぐに実行できることとしては、教科書の音読をしっかり行うことです。
小学生でしたら、ほとんどのお子様が宿題として音読がでると思います。
この音読、めんどくさいなぁと思いがちですが、国語の力をつける上で案外ばかにできないのです。
文章の区切りが分かって、漢字や言葉の意味が分かっていないとおかしなイントネーションになってしまいます。
国語の教科書にでてくる語彙をしっかり理解するだけでも、語彙力は身についてきますよ!
語彙力以外にも長文に慣れることができますし、音読の効果ってすごいですよ!
もしお子様が音読を面倒くさがってしまうようでしたら、親と交互に読んでみたり、今日は〇〇(子供の好きなキャラクター)になりきって読んでみよう!などとテンションをあげる工夫をしてみてはいかがでしょうか。
文章の要約を話すことで内容理解を深めよう!
【読解力チェックポイント③書かれた文章の内容を理解している ⇒NO!だった方はこちら】
次に、文章を考えながら読むくせをつけましょう。
ただなんとなく文を目で追う、と文章の構成や変化を意識しながら読む、は大きく違います!!
ここから長文読解の問題集を使用します。市販の標準レベルの問題集ならなんでもいいです。
しかし、いきなり問題を解くのではなく、本文を読んでみてこれはこんな内容のお話だったね、と親子で会話してみましょう!
要約というと紙に書いた方がいいんじゃないの?と思われるかもしれません。
ただ、我が家の息子がそうなのですが、紙に書くと一気にお勉強感がでて子供って嫌がるんですよね・・・
まずはハードル低く取り組みやすさ重視です。お父さんお母さんと楽しくお話してみるところからはじめましょう!
会話の中で意識するとよいことがあります。
物語文の読解で重要なこと
物語は登場人物の気持ちの変化が最も重要になります。
読解問題の場合、はじめはマイナスだった気持ちが、あるできごとをきっかけにプラスの気持ちに変化するパターンが多いです。
この、はじめはどんな気持ちだった、〇〇ということがおきた、その結果このような気持ちに変化した、の流れを意識しましょう。
文章によっては必ずしも大きなできごとは起きないかもしれませんが、登場人物の気持ちの動きが重要であることには変わりません。
気持ちは、嬉しい気持ち、と感情が直接書いてあるパターンは少ないかと思います。
表情や行動の描写、天候や周囲の風景描写から読み取ることもあります。
説明文の読解で重要なこと
説明文は筆者の主張、伝えたいことが何かを読み取ることが大事です。
最後に筆者の主張がくるパターンが多いですが、最初に主張がきて、それから理由を述べて最後にまた主張がくるサンドイッチパターンもあります。
説明文を読みながら、書き手はこんなことを伝えたいんだな、ここは理由を話しているんだね、これは具体例だね、などお話してみてください。
説明文はお子様にとって、はじめは読みにくいものかと思います。
ですが、慣れると意外と物語よりも簡単に読み取ることができるものです。感情の変化って複雑ですからね!
要注意!筆者の意見と自分の考えを混同しないで!
お子様に多いパターンで、筆者の考えと自分の意見を混同してしまうことがあります。
息子もそうだったのですが、自分はAと考えないから、この文章でも当然Bの意見のはずだ、と考えてしまうのですよね。
物語文でも同じことで、僕ならこういうことがおきたら嬉しいと思うから、登場人物も同じように感じるはずだ、と思ってしまう子、多いと思います。
長文読解には自分の考えは必要ありません!伝えたいことは全て本文の中から探しましょう!!
これ、めちゃくちゃ大事です!答えの根拠は全て本文にあります!根拠を探し出しまとめるゲームと思ってもよいかもしれません。
ここまで意識する点をまとめましたが、親子で要約を話しあう段階でこれらすべてが完璧である必要はないです!
ただぼーっと文字を目で追うのではなく、伝えたいことを考えながら読むくせづけができれば大きな進歩です!!
記号選択問題のパターンと解答手順を知ろう!
【読解力チェックポイント④長文読解問題で聞かれた問いかけの内容を理解し、記号選択問題は解ける ⇒NO!だった方はこちら】
ここまできてやっと、実際に問題に取り組んでみましょう!!
今回、記号選択と記述問題で分けましたが、一緒に取り組むほうがやりやすい方は同時で構いません。
読解問題が苦手なお子様にとって記号問題の方が取りかかりやすいかなとおもって、こちらを最初にしたまでです。
記号選択は適当に選んでしまいがちですが、本文中からしっかり根拠を探しましょう!
例えば、以下の2つの選択問題から本文に沿ったものを選ぶとします。(わかりやすく簡単な文にしています。)
A 〇〇は~~~で、ーーーーーで、××である。
B 〇〇は△で、ーーーーーで、◇◇である。
長い文章の場合は特に、まず文章を区切ります。この場合3つに分けます。
〇〇は~~~で、 / ーーーーーで、 / ×である。
〇〇は△で、 / ーーーーーで、 / ◇◇である。
このように文章を区切ると違いがはっきりしますよね!そして本文中から〇〇は~~~なのか、△が正しいのか根拠を探しましょう。
さらに、選択問題のテクニックもいくつかあるので覚えてしまいましょう!
一つ例をあげると、「絶対に、まったくない」といった強い肯定や否定文がきたときには要注意です。
世界にはりんごが好きな人がいる。は正解でも、世界の全ての人がりんごが好きだ。は間違いですよね。
ひっかけ問題にはよく知られているパターンがあります。
これらの問題のパターンや解答手順を楽しく学ぶために私がおすすめする本はこちらです。
角川まんが学習シリーズ のびーる国語 最強の読解力 文章が得意になる読み方のコツ
学習漫画なので楽しく読むことができます!記号選択だけではなく、記述問題含め長文読解全体の読み方のコツが分かりやすくまとめてあります。
先ほど角川の語彙力の本も紹介しましたが、角川の国語の学習漫画は面白さと分かりやすさを兼ね備えていて本当におすすめです!
もちろん、テクニックについては市販の参考書で学ぶ方法もあります。また、Youtubeにも探すと良質な動画がたくさんありますよ!「長文問題 選択問題 コツ」と検索してみましょう。
記述問題のパターンと解答の手順を知ろう!同じパターンの問題を連続して解いてみよう!
【読解力チェックポイント⑤長文読解問題で聞かれた問いかけの内容を理解し、記述問題にとりこぼしがない ⇒NO!だった方はこちら】
記述って、何を書いたらいいのと手が進まない・・・そんなお子様も多いですよね!
ですが、解答のヒントは本文中に書かれています。本文の中で必要なものを抜き出して組み合わせる作業です。
まず、解答の文章は末尾から決まります。なぜ~~ですか?と聞かれたら○○だから。いつ~~ですかと聞かれたら×のとき。と聞かれていることに正確に答える文面を作りましょう。
記述問題と一言で言っても、いくつかの種類に分けられます。
・書き抜きタイプ
・指示語の説明タイプ
・理由の根拠説明タイプ
・要点の説明タイプ
それぞれのタイプごとに解答パターンとテクニックがあります。
例えば、指示語の説明タイプの場合は下線部の前から対応する言葉を探していきます。
大抵は直前の文章から見つかるのですが、まれに離れた場所から見つかる難しいパターンもあります。
そして、見つかった言葉を下線部の指示語に置き換えて、自然な文章になっているか確認します。
これらのパターンについて、先ほど紹介した「角川まんが学習シリーズ のびーる国語 最強の読解力 文章が得意になる読み方のコツ」にも知識事項は書かれているのですが、記述問題の場合実践形式で問題に解き慣れてみることが必要になります。
オススメは、同じパターンの問題を連続して解いてみることです!
問題集のなかで、書き抜きなら書き抜きの問題のみ、理由説明なら理由の問題のみ抜粋して連続で解いていきます。
同じパターンの問題を続けて解くことで自分の中で問題を解くコツを実際に使えるものとして身につけることができます。
問題集は我が家はZ会や出口汪先生の論理エンジンが好きでよく使用していました。ただ、各ご家庭の好みでよいと思います。
ふくしま先生のふくしま式問題集も有名ですよね!
記述問題は成果がでるまで時間がかかるかもしれませんが、やったことは必ず力になっています!諦めず頑張りましょう!
時間制限を設けて文章の要約を書く練習をしてみよう!
読解力チェックポイント⑥制限時間に余裕をもって長文読解問題に正確に解答できる ⇒NO!だった方はこちら】
実際、前の章の記述問題が解けるようになった時点で読解力はかなり身についていると言えます。
ここから先は、さらに上を目指したい場合です。
例えば中学や高校受験で難関校を狙いたい場合、問題文はかなりの長文になってくると思います。大学受験の共通テストも近年ますます長文化が進んでいます。
そこで求められることは、決められた時間内に大量の情報をスピーディに読み込み、理解する力です。
なかには本が好きで自然にスピード感が身につく人もいるかと思います。
ですが、そうではない大半の人はひたすら訓練あるのみです。私は、要約文を書くことが効果的だと考えています。
要約文を書くためには、長い文章の中で大事なところを漏れなく見つける力が必要になるからです。
練習のためには、要約文専用の問題集を購入してもよいですし、中学受験の過去問を読んで解答を見ながら重要部位のチェックを行ってもよいでしょう。
近年、国語だけではなく、算数や理科、社会も前提条件を長文で提示する傾向があります。
つまり、読解力は国語だけに必要ではなく全ての教科に大事な力なのです。
頭が柔らかい小学生のうちに、ぜひしっかりとした読解力を身につけましょう!!
この記事がお子様の読解力アップに少しでも役にたちましたら幸いです。
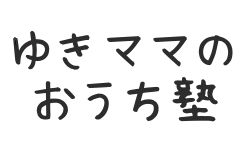
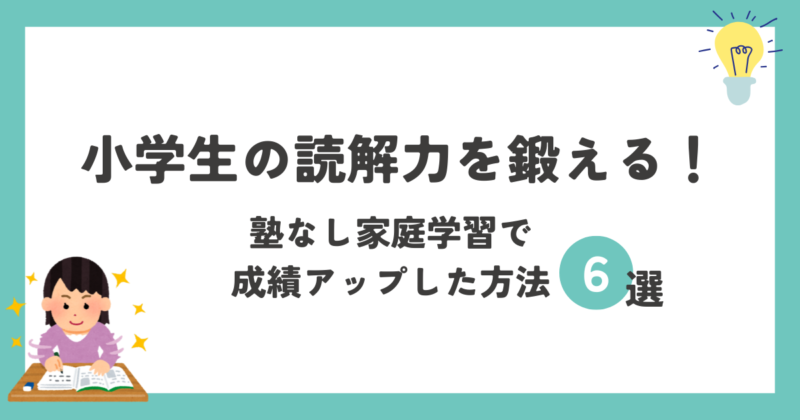
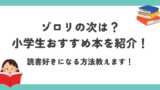
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4598edab.21fcef22.4598edac.96112e7e/?me_id=1213310&item_id=21021797&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0285%2F9784041130285_1_8.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

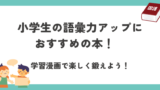
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45e4d1e3.8dbf480d.45e4d1e4.28a9600b/?me_id=1278256&item_id=24540046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5674%2F2000017155674.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

