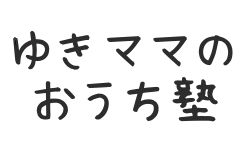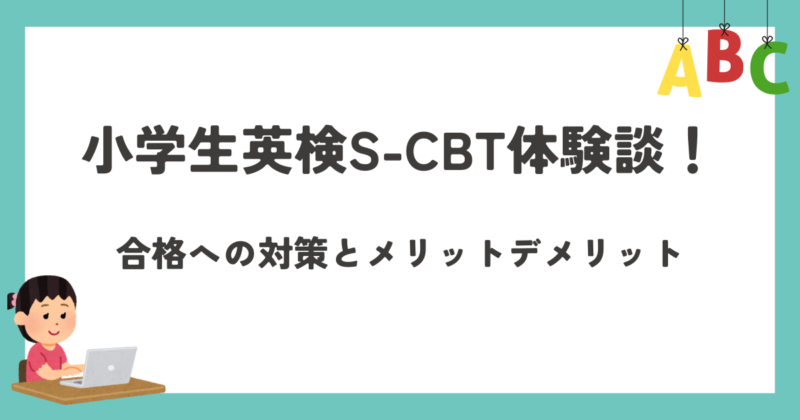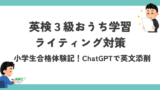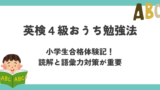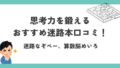小学生の我が子に英検S-CBTを受験させたいけれど大丈夫かしら・・・と不安を感じている保護者の方いらっしゃるのではないでしょうか?
そんな皆様へ、小学校6年生の息子が英検3級をS-CBT方式で受験し合格した体験談を紹介します。
実際に受験して感じた英検S-CBTのメリットやデメリット、そして対策としてどんな事前準備をしたのか、当日の注意点など具体的に書くので、参考になりましたら幸いです。
英検S-CBTのメリット
試験日が多い!
なんといっても試験日が多いことは嬉しいですよね!
従来型の英検の場合、6月、10月、1月の決まった日時しか選べません。
我が家の場合、従来型の日程は6月は運動会、10月は修学旅行と重なってしまいました・・・
さらに、息子の受験した英検S-CBT3級の場合、1日複数回の受験が実施されていました。
息子の受けた会場では朝、昼、夕方の3つの時間帯から選ぶことができたので、より細かく家庭ごとの予定に対応できますね!
4技能を1日で受験できる!タイパ良い!
英検S-CBTは面接も同日実施となります。
面接ってそのためだけに出向くだけではなく、待ち時間もかなりありますよね。。。
そんな余計な時間をかけずに1日でさくっと試験が終わることは魅力的です!
さらに、息子いわく受付から試験開始までがあまり待たずにスムーズだったそうです。
従来型の試験会場より、テストセンターの方が小規模な会場が数多く存在するためかと思います。
受験者数が多いほど、待ち時間って多くなる傾向がありますよね。
受験会場が駅近なことが多く、アクセス良い!
従来型の受験会場って、駅から離れていたりアクセスが悪いことが多いですよね。
少なくとも、私はそう感じています・・・
テストセンターは駅近なケースが多いです。
アクセスがいいことも含めて、タイムパフォーマンスが良いですね!
小学生の受験の場合、親が受付まで付き添うかと思いますが、駅近だと待ち時間を潰す選択肢が増えます!
親の都合ですが、待ち時間何もすることがないより、カフェに入ったり買い物をすることができる方が嬉しいですよね。
ライティングがパソコン入力できて圧倒的に楽!
試験内容の中で圧倒的なメリットはライティングが楽になることです!
パソコン入力に慣れているお子様に限りますが。
ただし、今は小学校でタブレット端末が配布されているので、タイピングに慣れているお子様は多いのではないでしょうか。
そして、修正したいときにすぐ消して、場合によってはコピーやペーストもできます。
文章の途中に1文追加したいときも楽々です。手書きの場合はいちいち消したり大変ですよね。
さらに、単語数カウント機能がついているので、今何単語書いたか数えずともすぐに分かります。
ライティングは文字数が決まっているので、このカウント機能はとても便利です!
万が一タイピングが苦手なお子様の場合でも、英検S-CBTで筆記のライティングを選択することもできます。
ただ、息子は圧倒的にパソコン入力がいい!と言っていました。
英検S-CBTのデメリット
事前にS-CBT方式のパソコン操作に慣れておく必要あり
S-CBT方式の英検の操作手順自体は実際、難しくはないです。
ですが、いきなり本番ぶっつけ!はやめましょう。
操作手順自体は、英検のホームページの英検S-CBT体験版で触れることができます。
各級ごとに体験版が用意されているわけではありませんが、試験の流れをつかむことができます。
パソコン操作自体は1度体験すれば十分かな、という難易度ですが、スピーキングと長文読解は練習が必要です。
この後詳しく書きます。
スピーキングは周囲の人の声が気になる可能性あり
試験4技能の中で最も従来型と違いがあるのがスピーキングです。
当たり前ですが、人と話すわけではないのでヘッドフォンから流れる音声の後自分でマイクから声を吹き込むことになります。
息子いわく、試験室は多少区切られていてヘッドフォンはしているものの、スピーキングの試験時は周囲の人の話している声が聞こえてくるそうです。
息子はさほど気にならなかったそうですが、お子様によっては集中力が途切れてしまうこともあるでしょう。
対策として、我が家ではスピーキングの練習問題をテレビをつけている部屋で行いました。
他に声が聞こえる中でスピーキングをすることに慣れておきましょう!
練習問題は英検S-CBT専用予想問題ドリルを使用しました。
この問題集はWEB模試が2回分収録されています。
2025年10月時点、現状英検S-CBT用の問題集はこちらのシリーズのみかと思います。
今後、もっとたくさんの問題集が発売されるとよいですね!
なお、英検S-CBTのスピーキングは話す時間に制限があります。
制限時間はさほど短くはないのですが、あまり長く悩んでいると何も話さずに時間オーバーということもあるので気をつけましょう。
パソコンの画面上で英文を読むことに慣れる必要あり
紙に書かれた英語の長文を読むことと、パソコンの画面上で読むことは勝手が違います。
英語の短文なら問題ない方が多いと思いますが、長文になると慣れが必要です。
私は受験も紙ベースで育ってきた世代なので、紙の文章の方が圧倒的に読みやすいです。
息子は、普段からインターネット上で英語絵本が多読できる教材で勉強しているので、抵抗はなかったようです。
パソコンの画面上で英文を読む練習は、さきほど紹介した英検S-CBT専用予想問題ドリルを使用してもよいですし、他の教材でもよいと思います。
例えば、オックスフォード・リーディング・ツリー(Oxford Reading Tree, ORT)など、インターネット上で英語絵本読み放題できるサブスクもあります。
なお、個人的な感想ですが、英検S-CBT専用予想問題ドリルのパソコン上の長文読解の画面はやや読みにくく感じました。
息子いわく、実際の本番の英検S-CBTの試験の方が長文の画面のつくりは読みやすかったそうです。
英検のホームページの英検S-CBT体験版もよく確認してみてください。(対象級ではない可能性もあります。)
英検S-CBT受験当日の注意点
保護者は試験会場に入室できない
英検S-CBTは時間、セキュリティ共に厳格だなと感じました。
早く会場に着いたから入っていいよということはなく、しっかり時間まで外で待たなければいけません。
保護者が入れるのは荷物を預けるロッカールームまでで、試験会場には受験する子供一人で入ります。
受付も子供一人で行いました。
なので、自分の名前や受験番号、試験会場を書く練習を1度はしておくとよいかと思います。
子供の場合、スタッフの方も優しく接してくださると思います。
小学校低学年のお子様の場合、試験会場の椅子が高さがあわない、ヘッドセットの調節が難しいということもあるかもしれません。
その場合、手をあげてお願いすればスタッフの方が助けてくださいます。
お子様に恥ずかしがらずに手をあげるようお話しましょう。
持ち物制限が厳格!
試験会場に持ち込めるものは、鉛筆と消しゴム、本人確認の受験票、ロッカーキーのみでした。
水筒、腕時計、受験票を入れるためのファイルも持ち込み禁止でした。
息子が試験を受けたのは夏場だったので、直前に水分補給をしておくか、トイレのことを考えて飲まないほうがいいか迷いました。
なお、試験中トイレ休憩はありません。
どうしてもトイレに行きたい場合、スピーキングとリスニングが終わった後、リーディングとライティングの時間なら席を外すことが可能かもしれません。
会場によると思うので、どうしても気になる方は事前に相談してみるとよいと思います。
トイレに行けたとしても、その退室時間分は試験時間が短くなります。
メリットデメリットをいくつも紹介しましたが、個人的には次に息子が受験するならまた英検S-CBTがいいなと感じています!
忙しい今どきのお子様に、時間の融通がきく英検S-CBTはとてもおすすです!
最後に、我が家のおうち英検対策について別の記事で詳しく書いているので、興味があるかたはどうぞ。