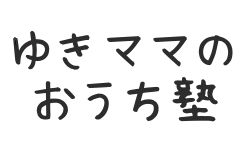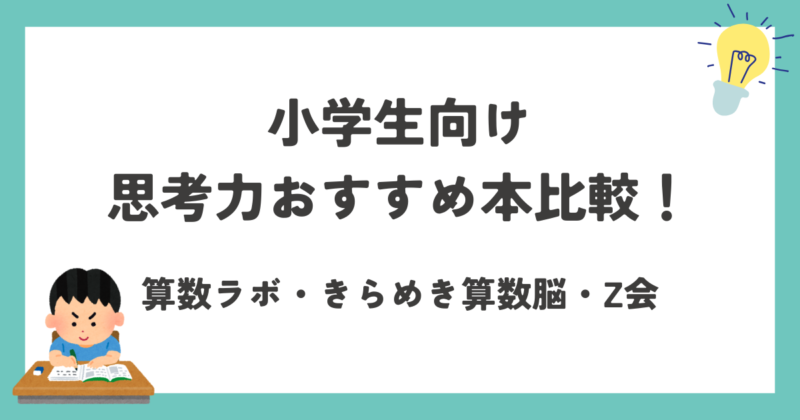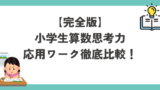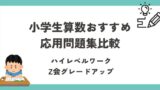近年の受験は思考力が重視されていると耳にします。
でも、思考力ってどうやって高めたらいいの?と悩ましいですよね。
書店には多くの思考力系ワークが並んでいますが、わが子に合うものはどの本か分からない・・・という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、わが家で息子が実際に取り組んできた思考力系ワークから厳選して、特におすすめしたい本を紹介します!
息子は中学受験する予定はないので通塾なし、取り組んでいるのはZ会の通信教育と市販のワークのみです。
ですが、先日の全国統一小学生テストでは算数で偏差値73をとることができました。
テストの問題は教科書に準拠していない、その場で設定を読み考える力を問うものが多かったです。考える力が少しずつ身についてきたのかなと嬉しく思いました。
思考力ワークの中でこれはおすすめできる!と考えた本は以下の3つです。
算数ラボ(思考力検定関連教材)
きらめき算数脳(サピックスブックス)
思考力ひろがるワーク(Z会)
それぞれの本の難易度、価格、特徴を簡潔にまとめました。価格は2025年5月時点のものです。
| 難易度 | 価格 | 特徴 | |
| 算数ラボ | 普通~やや難 | 990円 | ・良問揃いでお値段が安く、コスパよし。 ・問題は図形、文章題、推論問題とバリエーションがある。 ・余白が多いので、書き込みしながら考えることができる。 ・カラーではなく、キャラクターもいないので低学年の子供には単調かも。 |
| きらめき算数脳 | 難 | 2090円 | ・本の対象年齢に対して難問が多い印象。だが、良問揃い。 (対象年齢マイナス1の問題集を選ぶとよいかも) ・問題の設定は多様で、前提条件をしっかり読み込む必要がある。 ・オールカラーでカラフル。可愛いキャラクターが解説している。 ・値段は3商品のなかでは高め。 |
| 思考力ひろがる ワーク | やや難 | 1100円 | ・国語、算数、理科、社会をバランスよく配合した問題が揃っている。 ・ワーク別に難易度が分かれているが、きらめき算数脳の方が難しい印象。 ・オールカラーで配色は落ち着いている。キャラクターはなし。 ・穴埋めクイズのような問題もあり、楽しく取り組める。 ・図形問題は他2商品と比べて少なめ。算数の要素も少なめ。 |
この記事では、この3種類の本のおすすめポイント、そしてそれぞれの違いを比較して詳しく解説します。
また、思考力ワークを解くときのわが家の取り組み方についても紹介します。
お子様の思考力アップにお悩みの保護者のみなさまの参考になりましたら幸いです。
【小学生向け思考力ワーク徹底比較】経験談から特徴をお伝えします!
わが家で取り組んだワーク変遷は以下の通りです。
小学校1年生:算数ラボの10級(小学校1、2年対象)
小学校2年生:きらめき算数脳小学校1、2年生 ← 小学校1年生時点ではきらめき算数脳は難しかったため2年生から。
小学校3年生:Z会の思考力ひろがるワークの標準編 ← 理科や社会の要素も含まれているため、3年生から取り組んだ。
3年生以降は算数ラボ、きらめき算数脳、Z会と混ぜながら勉強を進めました。
それぞれの教材の特徴を以下に詳しく説明していきたいと思います。
算数ラボの特徴 メリットとデメリット
個人的に思考力系のワークの中で、最もコストパフォーマンスが良い本は算数ラボではないかと考えています。
そのくらい、とてもオススメな本です!
算数ラボのメリット
・問題のバリエーションが豊富で良問揃い。
算数ラボは、算数の問題の観点として5つ、考える力の観点として3つを含めた問題作成をしています。
算数の問題の観点 ⇒ 数と量、空間と形、変化と関係、データと不確実性、論理。
考える力の観点 ⇒ 情報、条件を使いこなす力、筋道をたてて考える力、物の形を認識、想像する力。
どの問題も、その問題ごとに条件を読み込み考える必要がありますが、不必要に難易度が高いわけではありません。
わが家では、問題集に表記された級の対象学年通りに取り組むことができました。
問題の難易度は3ステップに分かれており、初めのステップに取り組みやすい問題があります。
そのため、ワークを進める中で様々な問題に触れ、徐々にステップアップできます。
また、図形問題を強化したいな、という方向けに算数ラボ図形という別冊もあります。
・余白が多く、直接考えたことを書き込みできる
算数ラボの基本的な構成は1問1ページ、上半分に問題、下半分は余白です。
(もちろん、問題によっては2ページにわたることもあります。)
しっかり余白があるので、考えたことや条件の整理のメモを書き込むスペースが十分にあります。
特に、図形問題ですと直接書き込みできる余地が多いことは嬉しいですよね!
特に小学校低学年の間は書く文字も大きく、しっかり余白があることは大切かと考えています。
・お値段が安くてコスパがいい!
お値段も大切な基準の一つですよね!
算数ラボは、例えば10級ですと全部で113問、144ページのボリュームがあるにも関わらずお値段が990円です!
これは、なかなか驚異的なコスパの良さではないかと思います。
きらめき算数脳と比較するとお値段半分です。
算数ラボのデメリット
・カラーなし、キャラクターなしのため面白みに欠ける点あり
お値段相応といえばそこまでなのですが、フルカラーではありません。
また、子供が喜びそうなキャラクターはでてきません。
淡々と問題が並ぶのみです。
問題の質はお値段以上でとてもオススメの教材なのですが、お子様によってはつまらなく感じるかもしれません。
息子の場合はカラーではなくても気にならなかったようです。問題自体は面白いということでした。
きらめき算数脳の特徴 メリットとデメリット
きらめき算数脳のメリット
・問題の設定が多様で、前提条件をしっかり読み込む必要がある骨のある良問揃い。
きらめき算数脳は、算数ラボ以上に問題の設定が多様です。お買いもの、カラーの紙を折る、ボールを使ったゲームなどなど・・・
問題ごとに異なる設定をしっかり読み込む能力が必要になります。
中学校受験塾として有名なサピックスが監修しており、難易度高めですが非常に面白い良問揃いです。
1つの問題に対して、問1、問2、問3と順を追って深堀りした質問が提示されます。
問1で前提条件を理解しているか確認問題が出て、問2でその条件が変化したどうなるか質問され、問3で応用の問題が出るといった形式です。
算数ラボ、Z会の思考力ワークと比較すると一番中学受験の算数に近い形式なのではないかと考えられます。
・オールカラーでカラフル!可愛いキャラクターあり。
全ページカラーでとてもカラフルです!
ピグマ博士という可愛いキャラクターがいて、ヒントをくれたり解説してくれます。
また、男の子や女の子のキャラクターも問題の設定に応じて登場したり、図も綺麗に色分けされていてわかりやすいです。
驚いたことが保護者用の解説書までカラーでした。
保護者の解説書も分かりやすく、さすがサピックスだなという作りでした。
きらめき算数脳のデメリット
・お値段が高い
フルカラーであること、サピックス監修であることをふまえると仕方ないかもしれませんが、今回紹介する3つのワークの中で1番高いです。
ページ数は小学校1、2年生用の場合71ページで算数ラボの約半分です。(お値段は倍!)
もちろん、通信教育や通塾と比較するとお安いので、値段の差をどう感じるかは人によるかと思います。
・本の対象年齢に対して難問であるため、購入時には注意が必要
きらめき算数脳は小学1・2年生用、2・3年生用、とそれぞれの対象学年が書かれた発売されています。
そのため、小学校1年生のお子様にきらめき算数脳の小学1・2年生用のワークを購入しようとされるパパママさんもいらっしゃることでしょう。
ただ、要注意なのはこの場合お子様一人だけでワークを解くことができるのは、おそらくよっぽど優秀な子、あるいはすでに受験対策や他の思考力ワークで訓練済の場合のみだと思われます。
わが子の場合、小学校1年生の時に算数ラボ10級(小学校1年生向け)は一人で取り組むことができましたが、きらめき算数脳の小学1・2年生用は親の補助が必要でした。
そのため、きらめき算数脳1・2年生用は小学校2年生の夏休みから開始することにしました。
難関校を目指すサピックス基準の表記だと認識した方がよいかと思います。
思考力ひろがるワークの特徴 メリットとデメリット
思考力ひろがるワークのメリット
・国語、算数、理科、社会をバランスよく配合した良問揃い。
思考力ひろがるワークはZ会が監修しており、特徴として算数だけではなく国語、理科、社会の要素も複合的に含まれた面白い問題が揃っています。
印象としては、近年の共通テストの傾向を反映しているように感じます。(公式に記載されているわけではなく、個人的な感想です。)
きらめき算数脳が中学受験の算数に近いことに対して、思考力ひろがるワークは将来難関国立大を目指すことができるような柔軟な思考力を身につけることができるように思います。
思考力ひろがるワークは以下の6つの力の獲得を目指しているそうです。
思いつく力、いろいろと試す力、順序だてて考える力、整理する力、よく見る力、見ぬく力。
難易度としては算数ラボと変わらない程度でしょうか。表記された対象学年通りの本を購入して、特に困ることはないかと思います。
・問題がクイズ形式でゲーム性があり面白い!
思考力ひろがるワークの小学校1~3年生向けの基礎編には、あなうめ、しぼりこみ、ならべかえ、はっけんの4冊があります。
あなうめでしたら、漢字やことばの穴を埋めたり、数列のきまりを見つけて空欄を埋めたりします。
今回紹介した3つの教材の中では一番ゲーム性が高く、お勉強をしているというよりパズルを解いている気持ちになれるかと思います。
特に、低学年向けの基礎編は楽しいです!
高学年向けの標準編、発展編は文章量は多いですが息子の場合気にならないようで面白いと話しています。
・オールカラーで落ちついた配色。図、絵柄、文章がすっきりまとまって見やすく好印象!
問題の図面、絵柄の全体的な印象は、個人的にはZ会の思考力ひろがるワークが一番好きです。
オールカラーで子供にも親しみやすいですが、目がちかちかするような配色ではありません。
どちらかというと、サピックスのきらめき算数脳の方がカラフルで派手な印象です。絵柄のみの子供受けだと、きらめき算数脳の方がよい場合もあるかもしれませんが・・・
全体のまとめ方もすっきりしていています。
オールカラーで問題も1冊あたり50題あり、お値段1100円はコスパがよいのではないかと思います。
思考力ひろがるワークのデメリット
・図形問題は他2商品と比べて少なめ。算数の要素も少なめ。
思考力ひろがるワークの特徴で良さでもあるのですが、算数だけではなく、国語、社会、理科、低学年向けでしたら生活にかかわる要素が含まれます。
様々な分野を含んだ問題構成になっている分、純粋に算数としての思考力ワークを求めている方には不向きかと思います。
例えば、図形問題は算数ラボには豊富にありますし、きらめき算数脳にも含まれています。
ただ、思考力ひろがるワークでは1冊あたり数問程度、そして純粋に図形としてとらえるのではなく決まりを探す要素の一つとして図形がでてくるパターンでの登場もあります。
今回は思考力系ワークを中心に3冊ご紹介しましたが、その他に教科書に基づいた応用系算数ワークにも興味がありましたらこちらもご覧ください。
算数応用系ワーク全体を図や表を元にまとめた記事。
算数の教科書に基づいた応用問題集おすすめ紹介記事。
思考力ワークのおうち勉強方法を具体的に紹介します!
おすすめの思考力ワークをご紹介した次に、我が家でどのように取り組んでいたのか紹介します。
具体的には以下のステップです。
①息子が自分一人の力で何とか解ける難易度の教材を選ぶ。
②まずは、息子と一緒に問題を解いてみる。必要以上に教えたり話しかけることはせず、同じ机で別々に解く。スピード感は息子にあわせる。
③答え合わせをする。答えが間違っていた時は、親が教えるのではなく息子に解答を読んでもらう。そして息子から私に解答方法を教えてもらう。
④終わったら、難しかったけどよく考えられたね、○○のところを思いついたのすごいと思ったよ!いいアイデアがでたね。など具体的に褒める。間違えたときは怒るのではなく、今日の問題は◇を見つけることが難しかったねぇ、でも新しい方法を勉強できたね!と共感する方向で声をかける。
全体を通して言えることは、親が先生になって教えるスタンスではなく、子供主体で親は一緒に勉強して時には教えてもらう並走スタイルということです。
なぜかというと、親が教えるってなかなか難しくて、少なくとも我が家の場合親が違うといっても間違いを認めなかったり、話を聞かなかったりしたのですよね・・・
親が教えようとすると逆に解説をよく読まない分理解が浅くなってしまっていました。
親子関係って近い分、甘えもあるし難しいです。間違いを認めたくない、ということは性別も関係あるのでしょうか?男の子のメンツのような。
そのため、切り替えて我が家では親の私も一緒にワークを楽しんで解いていくよ!の共に頑張るスタイルが合っていたようです。
答え合わせの時のみ、息子が先生になるスタイルにしました。まずは息子が先に解答を読み、私は(もし答えを知っていても)何も知らないふりをします。そして、解答手順から順番に息子に解説してもらいました。
解説するにはしっかり理解することが必要です。そして、自分が教えるということが息子にとっては嬉しいことらしく、ノリノリで解説してくれています。たまには分からないふりをして、解説途中でヒントを追加してもらうこともあります。
思考力ワークを含め自宅で市販教材を学習することは、宿題や塾のような強制力がない分継続が難しいですよね。
ですが、しっかり取り組めば塾通いすることと遜色ない力を身につけることができます。
私は、下手に大人数のクラスに入るよりおうちワークの方が時間を有効に使えて良い面もあると思っています!
お子様の思考力アップにお悩みの保護者のみなさまの参考になりましたら幸いです。